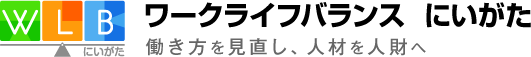ワーク・ライフ・バランスの本当の意味

ワーク・ライフ・バランスというと女性の育児休暇などの福利厚生をイメージされる方が多いと思います。本当は働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方のことです。
昔は3世代家族や親兄弟、親戚など頼る事の出来る人が近くに住んでいることも多く、コミュニティで支え合いながら、さまざまなライフステージの問題を分かち合い、生活することが常でした。
しかし、今は核家族化・少子高齢化・女性の社会進出に伴う晩婚化やキャリア形成などの社会環境の多様化が進み、男女共に仕事と家庭のバランスを取ることが非常に難しい世の中となってきています。
そのような中で、特に、女性雇用の面で妊娠・出産を経た女性が職場復帰や再就職をすることの難しさを痛切に感じ『能力や意力はあっても本人を取り巻く環境により、その人の特性と仕事がマッチングしない』という"機会損失"の現状が生じています。
ワーク・ライフ・バランスの実現により様々な状況に置かれている個人個人の事情や能力に応じ働き方を考慮し、既存の枠にとらわれない雇用を作り出す事が可能になります。
なぜ今ワーク・ライフ・バランスか

日本は少子高齢化へ急速に進んでいます。現在の労働力の中心は団塊ジュニアの男性ですが、働き盛りの男性従業員も親の介護者となる可能性が高く、介護休暇取得者の増加が考えられます。また、彼らが定年を迎えるころには晩婚化・生涯未婚率の増加などによる少子高齢化から労働力不足が深刻化します。今後の労働力確保が企業が生き残るための重要な鍵となります。そのための経営戦略が「ワーク・ライフ・バランス」です。
人種、性別、障害、年齢、家庭環境によらないダイバーシティ・マネジメント(人材の多様性戦略)により既存領域を超えたサービス及び商品を生み出すことで事業を拡大させていくことも可能です。
また「ワーク・ライフ・バランス」を実現させることで従業員のメリット、経営者のメリットのどちらも犠牲にすることなくWin-Winの関係を作ります。明日の新潟を元気にするためにワーク・ライフ・バランスの実現に一緒に取り組みましょう。
ワーク・ライフ・バランス導入のメリット
企業のメリット
1残業ゼロ-残業代の削減
チームのコミュニケーション向上による仕事のダブりを防止します。また、業務の見直しなどにより、ダラダラ残業などの無駄な仕事が減ることにより単位時間当たりの生産性が向上し、残業が減ります。また、それに伴う光熱費、タクシー代などの経費も軽減します。
2業務の偏りなし-従業員の不平等感の解消
業務の偏りは従業員の不満の素であり、仕事に対するモチベーションも下がりがち。また従業員のメンタル面でも影響は避けられません。ヒアリングやアンケートの実施により現状を把握し、業務の見直し、仕事の見える化などによる業務の偏りを解消することで、従業員の不満を解消します。
3個人依存からの脱却-業務がとまる危険性を回避
業務を知っているのは担当している従業員だけ、という会社が少なくないと思います。もし、その従業員に万一の事があったら・・・たちまち業務はストップし、営業機会の損失となってしまいます。仕事の見える化、業務チーム作成などにより業務を数人で共有していればそんな危険性を回避できます。
4離職者ゼロ-採用・教育コストの抑制、ノウハウ流出の防止
新人の採用・教育コストは決して小さくありません。仕事に慣れた女性従業員が出産、子育てなどの理由で退職することになれば企業にとってそれまでの採用・教育コストが無駄になります。また自社のノウハウに習熟したこの女性従業員が、子育てを一段落した後に育児支援の整った同業他社に再就職し、自社のノウハウを他社に伝えてしまう危険性もあります。
そのほか、仕事にやりがいを見出せず離職する従業員対策として、仕事の社会的意味づけを理解する教育プログラムの採用により、仕事の定義づけを行います。仕事の社会的定義づけのための教育と、仕事と家庭を両立できる仕組みを整えることで採用・教育コストを抑制し人材の流出を防止することができます。
5社会的責任を果たす企業-企業イメージの向上
取組みを社外へアピールすることにより、"企業イメージ"や"評価"が向上。特に最近の採用市場は少子化の影響により売り手市場がますます加速傾向にあります。学生も企業の従業員に対する姿勢を厳しく見ています。優秀な学生を採用するためには欠かせない施策です。
次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定を受けると「くるみんマーク」を使用することができ、働きやすい職場のイメージをアピールできます。(平成23年4月1日以降、常時雇用する従業員が101人以上の企業には、行動計画を策定し、一般への公開、従業員への周知、都道府県労働局への届出を行うことが義務付けられています。)
個人のメリット
1いくめんパパに変身!!-長時間残業からの脱却
チームのコミュニケーション向上による仕事のダブりを防止、業務の見直し、業務チーム作成などにより、残業時間を削減。お子さんの成長のためにご両親の笑顔は大切、減った残業時間を家族と過ごす・・・素敵なことです。
2一億総介護時代-介護休暇の対応
現在の労働力の中心は団塊ジュニアです。しかし、その親世代の年齢は70代。介護を必要とする方が増えて来る年代です。また、一人っ子、晩婚化、生涯未婚率の上昇により働き盛りの男性従業員も親の介護者となり得ます。そんな場合でも仕事の見える化などのワーク・ライフ・バランスを実現している会社であれば、代替要員との引継ぎが容易で、気兼ねなく介護休暇を取得することができます。
3働きたい人はいつまでも現役-活躍できる人を活躍できる場所で
少子高齢化により、シルバー世代も大事な労働力であり、定年までに培った仕事のノウハウは大事な資源です。業務グループの作成などにより、個人の生活に合わせた働き方が可能になりシルバー世代も安心して働けるようになれば、年金支給年齢が引き上げられても収入を得ることができます。
人種・性別・障害・家庭環境を問わず、多様な人材を活用するダイバーシティの推進で、誰でも活躍できる環境を作ることができます。
「企業のメリット」+「個人のメリット」=企業の生き残る条件
これまで私たちが持っていた「働き方はこうあるべき」という考えを一度リセットし、生活環境に合わせ、企業・個人(雇用者)の互いが柔軟な働き方の選択を可能にする事で、より豊かな社会のあり方が見えてきます。現代の企業・個人・地域を取巻く、健康、介護、人材の減少、少子高齢化などの問題の解決には、このワーク・ライフ・バランスの実現が必要不可欠だと考えます。
ワーク・ライフ・バランスの実現によって、企業・個人・地域、それぞれにとってのWin-Win-Winな環境を生み出す事ができます。
すぐ始めてみませんか?
内閣府 仕事と生活の調和推進室から平成22年に企業と働く者が仕事の効率化のために取り組むべきポイントとして「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「3つの心構え」と「10の実践」~仕事を効率化してめりはりワークを実現しよう~」を公表しています。これを参考にすぐにワーク・ライフ・バランス始めてみませんか?
内閣府 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「3つの心構え」と「10の実践」(PDF)
ワーク・ライフ・バランス導入時に想定される障害
経営者の認識不足

うちは業績がダウンしているから
そんなこと考えている余裕はないよ!!
業績ダウンの原因はお分かりですか?
組織が硬直化していませんか?
働き方の見直し、労働の効率化などにより改善できます。
先輩社員の妨害

私のときはそんな甘いことは
言わなかった。
残業が多い人、休まない人が良い従業員だと勘違いしていませんか?
意識改革セミナー実施などで社員の意識をかえていきます。
独身社員の非協力的態度
自分には関係ない。どうせ自分に
仕事が回ってくるんでしょ。
残業してでも早く仕事を覚えたい。

育児・介護休暇が必要になる可能性は誰にでもあります。ヒアリングなどで現状を把握し、業務見直しチーム作成などで業務の偏りを防止します。